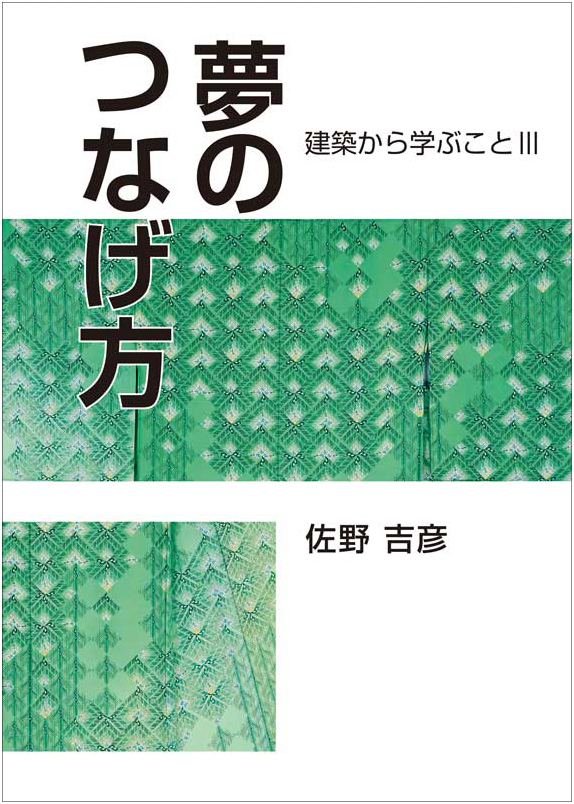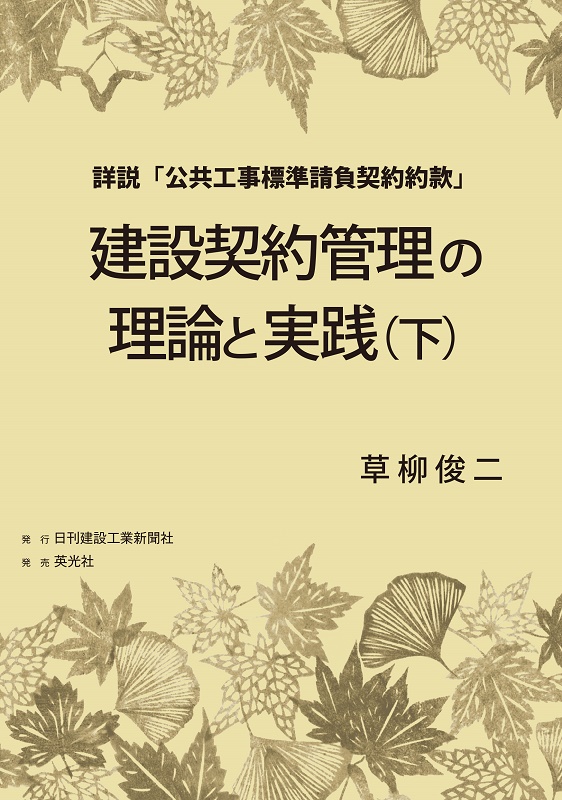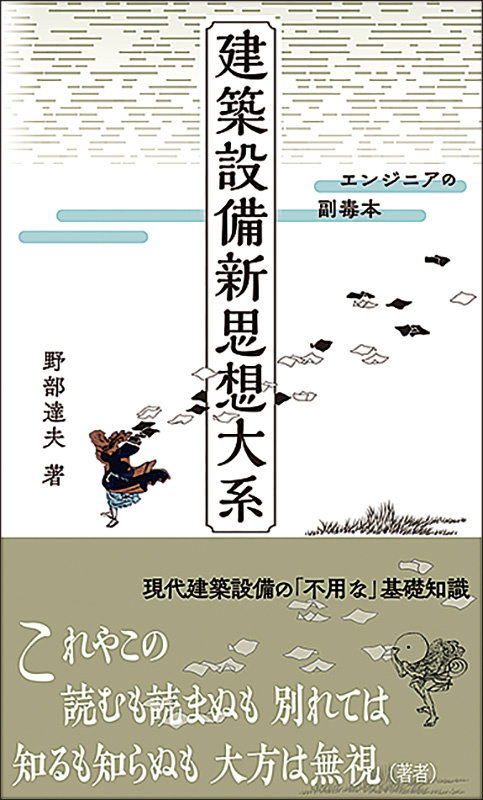◇実験繰り返し安全性担保
東京・渋谷駅周辺は、渋谷川が作りだしたすり鉢状の地形が特徴だ。大雨時に地下街が浸水したり、ガード下の道路が冠水して通れなくなったりする事態が頻発していた。渋谷川とどう向き合うかは、渋谷大改造の大きなテーマだった。
河川技術者として携わったパシフィックコンサルタンツ(パシコン)の並木嘉男国土基盤事業本部河川部流域計画室技術次長は「管理者から許可を得られる形に調整しながら、街づくりと水辺の一体化を考えた」と振り返る。関係者と議論の末、渋谷川の一部の位置付けを河川から下水道に変更し、東口地下に4000トンの雨水貯留施設を整備することになった。駅近くの暗渠(あんきょ)区間(約170メートル)の線形も変更が求められた。
具体的な線形が難題だった。旧東急百貨店の下を川が流れており、実現性と安全面での有効性の両立が求められた。「下水道基準を満たした断面をどう造るかが、水理計算だけでは再現が難しかった」(並木氏)。実験で確認するため、同社つくば技術研究センター(茨城県つくば市)に20分の1模型を製作した。
最初に想定していた線形では浸水の発生が想定される結果になった。線形や流下時の抵抗の発生状況などさまざまな条件や要素を考慮しながら、3~4年かけて膨大なパターンの実験を繰り返した。ようやく最適と考えられる形状を見いだし、発注者である東急電鉄や東京都ら行政関係者が実験を確認した上で線形などが固まった。
通常の都市開発は川の位置ありきでビルが建設されることが一般的。もともとビルの下を川が流れていて、官民連携で大改造するタイミングだったからこそ、川自体に手を加えて最適解を探る道が開けた。パシコン内でも、河川部門が街づくりや鉄道の部門と連携を深める良いきっかけになった。「プロジェクトの面白さとともに総合的な部門を持つ強さを感じた」(並木氏)。
時代の変化も大きい。高度経済成長期には川にふたをすることが多かった。当時としては快適な暮らしに向けた最善の策だったが、成熟社会へと移り変わる中で、水と親しむことを社会が求めるようになった。
渋谷駅の先からの約600メートルは、東急東横線の地下化で生まれた線路跡地などを生かして「渋谷リバーストリート」が整備された。ビルの裏側の存在だった渋谷川に対して街が開いてきている。「川を生かす時代になったからこそ、人や街がもっと川と融合できる形を考えたい」(並木氏)。より良い在り方を模索する挑戦はこれからも続く。