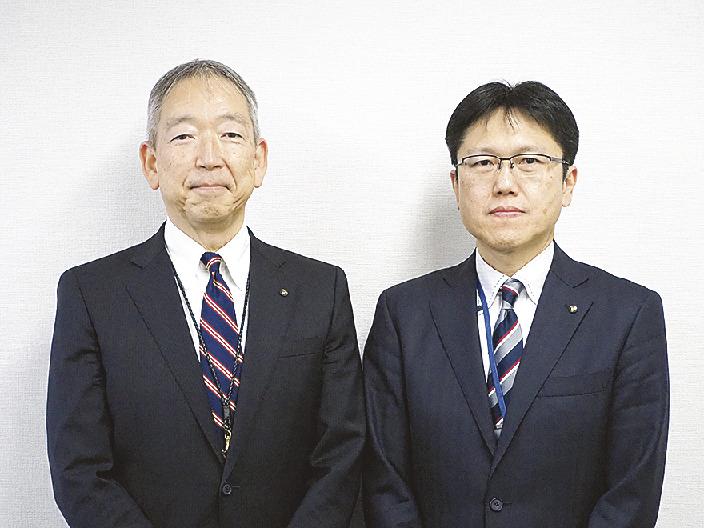首都高速道路(首都高)の中央環状線が3月7日に全線開通10周年を迎えた。中央環状線は葛西JCT(東京都江戸川区)から大井JCT(同品川区)までの延長約47キロを、都心を囲むように配備されている。整備を巡っては環境問題への対応や技術的挑戦など、区間ごとに異なる苦労があった。開通後は渋滞解消や交通利便性の向上で大きな経済効果を生んでいる。
首都高は、都心の一般道の渋滞緩和を目的に計画され、1964年の東京五輪前から中央環状線の内側区間の一部が先行して整備された。後に各放射路線が東日本高速道路会社などの都市間高速道路と接続し、郊外から都心部へ向かう車を迎え入れる役割を担っていく。その結果、首都高内で激しい渋滞が生じ、都心部を迂回(うかい)する環状道路が求められ、中央環状線の整備が進んでいった。
中央環状線は77年、5号池袋線の板橋JCT(東京都板橋区)~熊野町JCT(同板橋区)が開通したのを皮切りに整備が進んでいった。最初に都市計画手続きに着手したのは西側の青梅街道~大井JCT間だったが、環境問題が原因で休止した経緯がある。当時は道路トンネルにシールド技術を用いることが一般的ではなかったため、首都高は河川などの公共空間上に高架橋を建設していた。同区間は市街地を通るため、騒音や排ガスなどの問題で高架橋建設による計画は実現しなかった。
東側の葛西JCT~江北JCT(同足立区)間で整備を進め、87年9月に開通した荒川線は、河川管理者から許可を得て、荒川と中川に挟まれた中堤に高架橋を建設しており、河川の堤防と一体的に整備した。
2002年12月に開通した江北JCT~板橋JCT(同板橋区)間の王子線では、同社初となる東京都条例の環境影響評価(環境アセス)を実施。「当時は解析用のパソコンソフトが普及しておらず、先例もなかった。手探りで整備に携わった先輩方は大変な苦労をしたはず」(首都高速道路会社の草壁郁郎計画・環境部長)という。
10年3月までに段階的に開通した熊野町JCT~大橋JCT(東京都目黒区)間の新宿線では、当時画期的だったシールド工法を採用し、後の工事で使用する多彩な新技術が開発されていく。出入り口をシールドトンネル構築後に地上から切り開いて施工する開削切り開き施工や、シールドマシンを内回り線施工後にUターンさせ、外回り線を施工する工法などが採用された。「発注者側と請負業者側が一緒になって勉強し、この現場での切磋琢磨(せっさたくま)が後の新技術の開発につながったはず」(原隆広東京西局長)という。
最後の整備となった大橋JCT~大井JCT間の品川線は事業化最初期の環境問題を踏まえ、シールド工法で地中に整備した。この頃にはシールド工法も技術的に成熟し、長距離の施工や地中での切り開き施工が可能になっていた。
中央環状線は現在、1日に約33万台が通行している。首都高速会社は中央環状線整備で生じた経済効果を、年間約8200億円と試算。首都高は東京23区の貨物輸送量の約3割を担っており、中央環状線はそのうち約4割の貨物車が利用するため、都内の物流を支える側面もある。
羽田空港へのアクセスが容易になったメリットも大きい。開通前は熊野町JCT~羽田空港間で約50分かかったが、現在は約34分に短縮された。医療施設へのアクセスが早くなり、救急搬送にも貢献している。
整備後は中央環状線より内側の高速道路で渋滞が緩和し、事故件数は00年から23年にかけて約6割も減少した。事故や災害、補修工事で都心環状線経由ルートが通行止めの際、迂回路として利用できるリダンダンシー機能も有する。
同社は完成した道路の維持管理にも力を入れる。大井JCT~熊野町JCT間を結ぶ山手トンネルは、全長約18・2キロの日本一長い道路トンネル。多くの防災設備を配置し、開通後に大規模な火災や崩落などは発生していない。「建設当初から特に丁寧に施工した証だ。施工を担当した先輩方の技術力には感心せざるをえない」(草壁部長)。「次の世代につなぐため、今後はトンネルの維持管理技術を磨いていくことが重要」(原局長)と意気込む。
同社は3月8日、全線開通後に入社した若手社員を中心に、大橋JCTで10周年記念イベントを開催。中央環状線の歴史を振り返る動画やライトアップなどで、今後の整備への思いを新たにした。