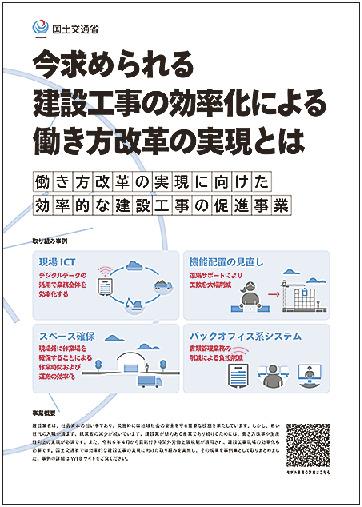時間外労働の罰則付き上限規制の建設業への適用から1年がたった。建設工事は土木や建築で現場の特性が異なり、工事規模の大小もさまざま。依然多くの課題があり、現場作業を効率化し生産性向上を成し遂げるのは一朝一夕には難しいのが実情だ。全国各地の建設業者が現場従事者の労働時間削減に取り組む中、国土交通省はICTの活用や現場運営の工夫で効率的な施工を目指す個別現場のモデル的な取り組みを支援。2024年末までの成果を30件の事例集として公表した。
国交省は時間外規制の適用を踏まえ「働き方改革の実現に向けた効率的な建設工事の促進事業」の実施費用を23年度補正予算で確保。建設現場では▽効率的な工事が必ずしも実施されていない▽適切な工期・価格による契約が必ずしも実現できていない▽生産性向上に寄与するツール・仕組みの導入に対する費用負担や効果が理解されていない-といった問題点があると指摘し、効率的な建設工事の試行に取り組む際の掛かり増し経費を負担する形でモデル事業を支援した。
個社単独だけでなく、発注者や元請・下請などと連携した取り組みに重点を置き採択したのがポイントだ。例えば道路造成工事の建設発生土の搬出にデジタルデータを活用した事例では、ダンプトラックごとに積載量を登録した無線通信デバイスを配置。バックホウの積み込み重量をリアルタイムに計測し、各ダンプの積載量に合わせた効率的な積み込み作業を実現した。ダンプドライバーと建機オペレーターの労働時間が削減されるとともに、運搬効率向上で工期短縮につながる効果もあった。
国交省はモデル事業を通じ、取り組み内容を▽現場ICT(ICT機器やデジタルデータの活用による現場作業の効率化)▽機能配置の見直し(建設ディレクターや外注の活用による書類作成などの業務負担の平準化)▽作業場・駐車場・宿舎など確保(現場外のスペースの活用による現場作業や資機材運搬の効率化)▽バックオフィス系システム(工程管理や原価管理のシステム導入によるバックオフィス業務の効率化)-の四つのカテゴリーに分類する。
あくまで民間提案をベースとしながらも各モデル事業の現場を実証実験のフィールドと位置付け、試行中に生じた課題への対応策を一緒に探る「伴走支援」に当たった。労働時間の削減効果などを定量的に算出し、試行を参考とする建設業者などに向けて期待される効果を分かりやすく明示。モデル事業を終えた建設業者の声から、取り組みの改善点や他現場への展開可能性も示した。障壁の一つとなるデジタル機器やソフトウエアのコスト負担には、中小企業庁の「中小企業省力化投資補助金」や「IT導入補助金」を活用する方法を紹介する。
デジタル化とは別に現場運営の工夫の一例として、配管工事現場やクレーン車両を用いた現場での「スペース確保」の取り組みも紹介する。工事全体の後工程の配管工事では、現場状況に応じた調整作業が頻発し、作業時期の波や工数の偏りが生じる。そこで現場外に倉庫を借りて配管のプレハブ加工を施した。結果として現場作業が減り、現場作業員数は半減。無駄な運搬や作業員の待機時間が減る効果もあった。
クレーンの回送時間や現場入場の待機時間を解消するため、元請との交渉で現場内にクレーンの駐車スペースを確保する試行も行った。工事進捗によってスペースを確保できない場合もあり、元請との緊密なコミュニケーションが不可欠と言える結果となった。
今回のモデル事業は公共土木工事の現場が比較的多く、民間建築工事のさまざまな現場条件に対応した好事例を増やすことが今後、求められそうだ。現場内の元請・下請だけの取り組みでは限界がある場合、民間発注者との連携を模索することも今後の課題だ。
□個々のニーズ踏まえ参考に/動画やパンフレットで周知□
国交省はモデル事業の紹介動画やパンフレット=画像=を作成し、事例集の普及を図る。四つのカテゴリー別に、元請向けの取り組みか、専門工事業者向けの取り組みかを分かりやすく整理。個々の現場ニーズを踏まえ、興味がある取り組みを参考にするよう働き掛ける。
建設業者の働き方改革とは異なるものの、モデル事業の一環で能登半島地震の被災自治体のマンパワー不足に対応した働き方改革の取り組みも試行した。災害復旧工事発注の本格化を見据え、国や県、市町村が参加する「発注者調整会議」の運営を円滑化するマネジメントシステムを構築。関連工事の情報を一元管理し、関係者間の調整にかかる負担軽減を期待する。